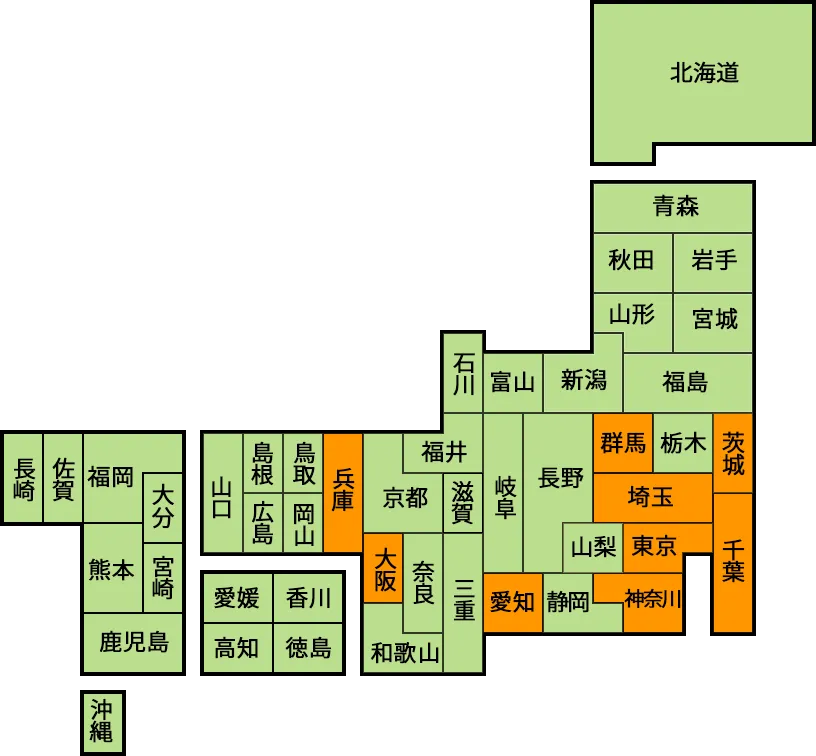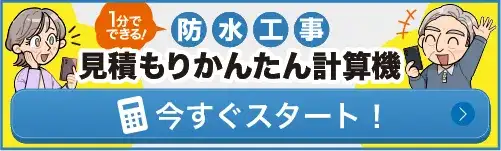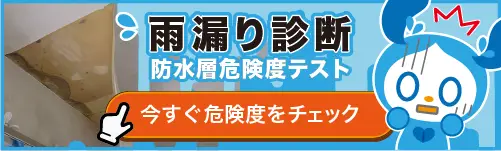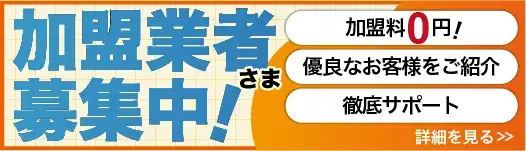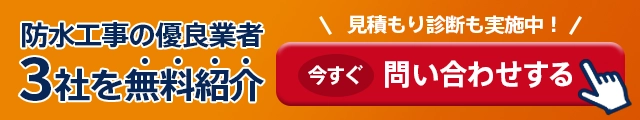雨漏りの原因と改善方法・防ぐポイント・スガモリ現象との違いも解説
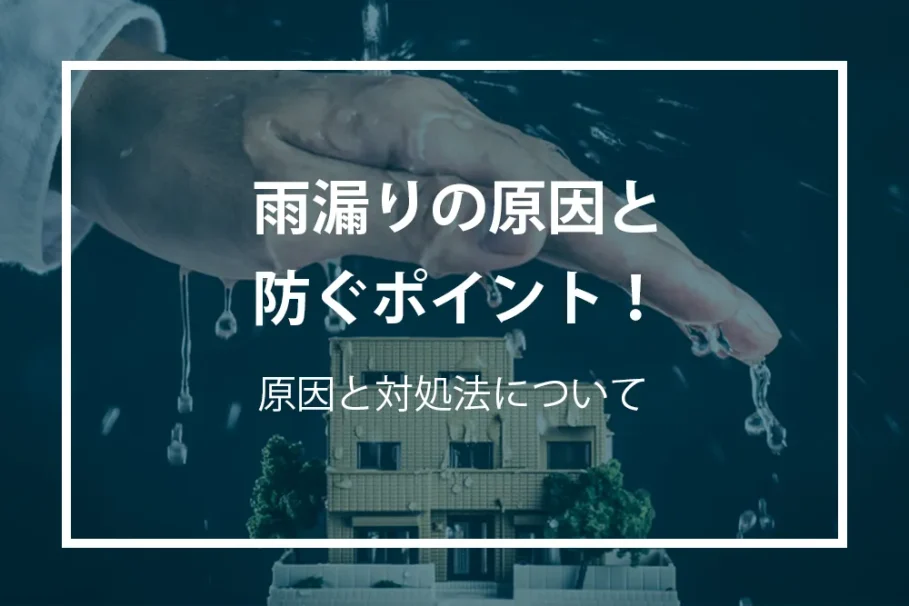
貴方の家の天井からの水漏れ、雨漏りですか?スガモリですか?それとも配管トラブルですか?
住宅を購入して数年、または数か月経過したある日、壁・天井からの水漏れ・・・。
すごく驚くと思いますが、色々な人が経験している身近な事故なのかもしれません。
素人目から見ると全てが「壁・天井から水が落ちてきた」となるのですが、
詳細な調査をするといくつもの原因があります。
今回はその中の「雨漏り」について防水アドバイザーの福島が解説します。

■福島 慎介
神奈川県出身 一般社団法人 防水工事推進協会 代表理事 防水アドバイザーとして12,000枚以上の見積りや防水工事を診断 お客様の立場・視点から分かりやすくお伝えします。
1.雨漏りの原因
雨漏りのトラブルにもいろいろと原因があります。以下に箇条書きであげて行きます。
■屋根板金の劣化(錆等)により板金に穴が空いた事による雨漏り
■建物の納まりが悪い事(施工不良・不備)による雨漏り
■小屋裏換気口(小屋裏の湿度を下げる為の換気口)が原因の雨漏り
■外壁の劣化による壁からの雨漏り
簡単に思いつくまま書き上げましたが、すぐに色々な原因が思いつきます。
2.雨漏りを防ぐためのポイント
上記では、雨漏りの原因をご紹介しました。
しかし、調査・補修となると、
経験を積んでいる建築士・施工監理士等の方でさえ、頭を悩ませると聞きます。
補修の方法に関しても「トライ&エラー」が多く、
家を建てて頂いた建築会社が無償でやってくれるのであれば
「何度でも直るまでやって下さい」となるのですが、
調査・補修の度に金額を請求されたら大変です。
そこで、雨漏りを未然に防ぐ為に今からやっておく事を取りまとめて行きます。
2-1.屋根からの雨漏りを防ぐためにやれること
多くの住宅は、板金又は新築であれば
ガルバリウム鋼板
と言われる物で
屋根が作られている事が多いと思います。
(板金の下部には水の浸入を防止する防水シートと言う物が敷かれています)
実は板金は厚さ0.35mm程度の物が多いのです。
0.35mmと聞いて驚いている方も多いかもしれません。
身近な薄い物で言うと
一円玉の厚さ約1.5mm
シャープペンの芯0.5mm
上記の物より薄いと言う事になります。
元々物がぶつかる所では無いので、
外的要素からの穴等はそんなに心配は無いかもしれませんが、
やはり常に水のあたる部分。
金属なので錆が発生する事も多々あります。
そこで、錆を発生させない為に
塗装を行う事でリスクを少しでも減らす
事が可能です。
メンテナンス時期は、昔の俗にいう
トタン屋根と言う物であれば約10年程度毎
。
ガルバリウム鋼板であっても15年程度
でしょうか?
(メーカーでは20年等保証をつけている場合もありますが)
ご自身の建物の状況を確認して常日ごろからのメンテナンスをお勧めします。
2-2.外壁からの雨漏りを防ぐためにやれること
最近の外壁では、
サイディング
と言う物が主流となっています。
サイディング自体は14mm程度の物が多いです。
実際は、サイディングにて水を抑えているのでは無く、
サイディングの内側に防水シートが貼られています。
しかし防水シート自体は0.2mm程度の物が多く、
外壁の劣化によりサイディングの内部に水が入り込み、
そして0.2mmのシートの穴等から水が浸入します。
そして建物内部の色々な隙間から水が出てきます。
さて、今からできるメンテナンスは何でしょう?
防水シートは壁の中なので確認する事が出来ませんが、
サイディング自体は確認できます。
サイディングは10~15年程度で塗膜の劣化が生じます。
塗装が劣化すると
チョーキング現象
と呼ばれる古くなった塗膜が粉状になる現象がでます。
壁をご自身で触って頂き、粉がつけば塗膜の劣化の可能性があります。
サイディングの劣化を防ぐ事で、少しでも内部への水の浸入を抑える事に繋がりますので、
こちらも常日頃からの状況確認、
10年程度でのメンテナンスが必要
になります。
2-3.家を建てるときにやれること
さて、現在家を建設中の方も多いですよね。
「ここを直してほしい」等を伝えるには専門的な知識が必要です。
そこで、ある程度効果的な方法として、
【現場にいつも顔を出す】
と言う方法があります。
関係無いように見えますが効果的な方法になります。
まず建築会社含め、職人さん達の気が引き締まります。
こちらは何も煩い事は言わなくても、職人さん達に緊張感を持たせる事が大事です。
そして
何かを発見したら小さな事でも聞いてみる
事が良いと思います。
ここは、【職人と建物】という形よりも【人と人】との関係性を大事にする事が大事ですね。
それを踏まえて良い建物が出来上がると思います。
2-4.保険を使って直すこと
お住まいの住宅に火災保険を掛けているのであれば、
強風や豪雨・台風等の災害により生じた雨漏りであれば保険適用になるかもしれません。
又、新築を建築した方であれば
建築会社に10年間の瑕疵責任
という物があります。
ほとんどの新築住宅は瑕疵保険と言う物に加入しており、【雨水の浸入する部分】に関して保険の対象になります。
ご自身の加入されている保険を一度確認して見てはいかがでしょうか?
3.雨漏りに似ているスガモリ現象
スガモリ
・・・あまり聞きなれない言葉ですね。
寒冷地特有の雨漏りに似た症状なのですが、スガモリとはどのような現象なのでしょうか。
4.スガモリ現象が起こる原因
寒冷地では、雪解けの時期(春先頃)に雨漏りに似たスガモリに悩まされる事が多いです。
寒冷地で春頃に起こる、天井からの水漏れに関しては、
殆どがこの「スガモリ」による現象の可能性が高いです。
下記になぜ起こるのかを書いて行きます。
① 冬に屋根の上に雪が積もります。
② 断熱性能が低い場合、
屋内からの暖気が屋根に上がる事で屋根の上の雪を溶かします。
(又は春先の日中等、気温が暖かくなり屋根の上に積もっていた雪が解けだします)
③ 夜等外気温の低い時間帯(又は気温の低い日)に
溶けた水が凍りつきます。
④ 凍り付いた水が
屋根の上又は軒先等で凍り付きます。
[氷の堤防=
氷堤(ヒョウテイ)
と言います]⑤ 次の日等②~④が繰り返し起こりますが、元の氷堤がある為に段々と氷堤が大きくなっていきます。
⑥ 氷堤に遮られ、軒先から落ち切らない水が、
板金の隙間等より建物内部に入り込んできます。
(屋根や建物には数mm単位の隙間はありますので、そこより[毛細管現象]により入り込みます。
⑦ そして
屋内に水漏れが生じます。
上記について少し理解して頂けましたでしょうか?
このような症状が寒冷地特有のスガモリと言う症状になります。
5.スガモリ現象の解決策
スガモリは寒冷地の無落雪屋根と言う屋根の場合に多くみられる症状なのですが、
スガモリが起こった場合にはどのような解決策があるのでしょう。
5-1.強制的に溶かす方法
無落雪屋根には、屋根の上に水を抜くための排水口があります。
そこに向かい屋根勾配がつけられている工法となります。
屋根の上には排水溝(水の流れを排水口に向ける為のレーン)が取り付いています。
排水溝が凍り付いたりする事でスガモリ症状を起こしますので、
排水溝又は排水口が凍り付いてしまわないように、強制的に溶かす方法があります。
排水溝・口内に
排水路ヒーター
と言う物を取り付け、
電気熱により強制的に溶かす方法が効果的
です。
基本的には雪の降る11月頃に屋内にあるスイッチをオン、
4月頃にスイッチをオフにする事でほとんどのスガモリ症状は解決します。
この場合は半年位の間ランニングコストが増しますので、
コスト面を視野にいれての設置検討をお勧めします。
寒冷地の電気業者等は使い慣れている商品となりますので、相談すると良いでしょう。
5-2.二重屋根にする方法
今現状の屋根の上に、
空気の流れ道(空気層)を作り、
屋内の暖気が直接屋根上に届かないようにする方法
です。
新規の屋根と既存の屋根の間には、外気温と同じ空気が流れますので新規屋根に暖気が届きません。
暖気が届かない事で氷堤が出来づらくなる
ので、スガモリが起こらなくなります。
仮に新規の屋根上で水漏れが起こったとしても、
既存の屋根にて水漏れを防ぐダブルの屋根防水となります。
5-3.屋根改修による方法
無落雪屋根の工法になっている建物を
思い切って三角屋根等にする方法
です。
構造的には改修可能かと思います。
建物全体の改修も検討されているのであれば、
全体計画の中で屋根形状の改修もするのが良い
のかもしれません。
敷地に対する建物の検討や、構造的な検討、法律的な検討等、検討箇所は沢山ありますが、
そこは素人が考えても無理なので、プロに任せてしまいましょう。
5-4.建物断熱性能改善(断熱改修)による方法
根本的なスガモリ対策としては屋内からの暖気を、屋根に抜けさせない事が大事になります。
断熱改修を行う事で暖気漏れを防ぐ事が可能
です。
昔の建物であれば、天井裏の断熱材の厚さが小さい事が多いと思います。
その
断熱材を厚く、又は新しい物に取り換えを行う事で暖気漏れを防ぐ
事ができます。
断熱改修を行うのであれば、併せて壁・床下等の断熱改修を一緒に行う事
で、
夏涼しく・冬暖かい快適な暮らしになります。
一緒に、排水路ヒーターの設置や、屋根板金の葺き替えも検討すると良いでしょう。
5-5.スガモリ改修のプロに相談
上記に解決方法・改修方法を書きましたが、
ご自身の建物の状況を一度プロに確認してもらい、方法を決めていく事が良い
と思います。
建物により、最善の改善方法が違います。
建物のプロ(スガモリ改修に慣れているプロ)に相談する事で
一番良い提案を受けられると思います。
6.スガモリ現象、建物性能の改善には断熱改修がお勧め
スガモリの症状・解決方法について書いて行きましたがご理解頂けましたでしょうか?
私は、
建物の性能を改善(断熱改修)しつつ、排水路ヒーター設置等を行う事が良い
と思います。
スガモリは寒冷地特有の症状ですが、
夏の厚さ改善(外部からの熱の侵入や、屋内の冷気の外気への逃げ)の為にも
寒冷地だけではなく、
日本共通的に断熱改修はお勧めします。
市町村によっては助成金等も出る事もありますので、一度確認してみると良いでしょう。
7.屋根の種類について
屋根にはいろいろな種類、色々な葺き方があります。
屋根の形の種類をご紹介します。
7-1.切妻屋根
四角い建物の上に三角が乗っかる屋根。
屋根面が2面で構成されている形状になっています。
7-2.寄棟屋根
屋根の頂上部より4方向へ屋根面が分かれている屋根の事を言います。
屋根面が4面で構成されています。
7-3.片流れ屋根
屋根が1面で構成されています。
名前の通り片方のみに屋根勾配がついています。
デザイン的には綺麗な納まりになります。
7-4.方形屋根(ホウギョウヤネ)
正方形の屋根が一方に集まる屋根を言います。
ピラミッドをイメージすると解りやすいです。
7-5.無落雪屋根
名前の通り、雪が落ちないように屋根の上に乗せておく屋根の事をいいます。
寒冷地特有の屋根の工法となります。
8.屋根の雨漏りリスク
ガルバリウム鋼板等で施工する一般的な木造住宅の場合には
上記の寄棟屋根、切妻屋根、片流れ屋根、法形屋根の場合が多いでしょう。
上記の場合は
屋根勾配が生じているので、雨漏りのリスクは少なくなります。
又、屋根の構成が少なければ少ないほど角等施工上難しい部分が少なくなるので、
リスクは少なくなります。
(上記の種類で言えば、片流れが1面の屋根で構成されていて少ないと言えます)
9.金属屋根の種類、葺き方
又、金属屋根の葺き方にも種類があります。
9-1.瓦棒葺き
屋根の流れ方向に瓦棒心木を継目として、金属板を組み合わせて行く工法になります。
緩勾配でも比較的安心なので金属屋根で一般的に施工されている工法です。
9-2.立はぜ葺き
屋根の流れ方向に長尺の金属板を配置し、両端のハゼを締め付けて施工する工法になります。
ハゼを締め付ける職人のテクニックが必要になります。
これも一般的に施工されている工法になります。
外観は瓦棒葺きに似ている工法です。
9-3.平葺き
小さい単位の金属板を重ねて、4方向に曲げられたハゼに構成していきます。
一文字葺きや菱葺き等デザイン性のある物を作る事が可能です。
外壁等で使う事もあります。
ハゼ部分が多くなるので、折り曲げを行った部分に水が溜まりやすく、
錆等を生じる可能性もあります。
9-4.折板葺き
波型に加工した金属板で屋根を敷いていく工法です。
一般の住宅ではほとんど用いられません。
工場等で多くみられる工法となります。
10.雨漏り防止の為に屋根の形、葺き方をよく検討しましょう
屋根の形の種類、屋根の葺き方の種類を紹介して行きましたがイメージが湧きましたでしょうか?
上記を見ると、片流れ屋根の瓦棒葺きの工法が雨漏りの少ない工法となるのではないでしょうか?
雨漏りを防ぐ為には、計画段階での屋根の形、工法をよく検討する事が必要になります。
新築住宅を計画又は購入を検討の際には検討するようにしましょう。
11.危険!雨漏りが木造住宅に与える大きなダメージ
木造住宅は、きちんと手入れをしていると100年以上使う事が出来ると言われています。
疑問に思う方もいるかもしれませんが、お寺や神社は100年以上もっている建物が沢山あります。
それは、木造の丈夫さを表しています。
木造の建物はモロく弱いと思う方もいるようですが、
実は乾いている状態ですととても丈夫な建物です。
しかし、雨などに塗れてしまうと、一気にダメージが強く与えられてしまい、
非常にもろい建物に変化させてしまいます。
そんなもろい状態を作ってしまうのが、雨漏りです。
雨漏りは、見受けられたら即座に修理しないと大変面倒な状態にしてしまいます。
雨漏りが起こしてしまう恐ろしい現状を、ご紹介します。
11-1.建物の寿命を短くする
雨漏りは、建物に浸み込んでしまった雨水がポタポタと形になって発生します。
それを踏まえると、
雨漏りに気付いた時点で建物はかなり酷い状態に陥っている
と言えます。
ポタポタ雨漏りに気付いた時には、すでに建物の構造材に大きな影響を与え、
寿命を短くしている可能性があります。
11-2.シロアリの餌食になる事も
木造住宅に潜みやすいシロアリは、湿気が大好きです。
雨漏りを起こしている建物は、湿気の温床です。
シロアリの絶好な環境ですので、シロアリが大量に侵入し住処にしてしまいます。
構造的に重要な部分をシロアリが食い尽くしてしまい、建物の倒壊も免れません。
11-3.カビ大量発生で健康被害
雨漏りにより構造材は湿気に侵され、カビが大量に発生
してしまいます。
カビが大量発生すると、アレルギー持ちの方には辛い状態となってしまいます。
健康な方でも、カビの強烈な臭いに具合が悪くなってしまいます。
11-4.定期点検、早めの対応が大切
このような最悪な建物にならないよう、
まずは定期的な屋根の点検を行い、
<s
少しでも不具合を発見したら即補修を行うようにしましょう。
</s
補修の早さ次第で、いつまでも快適に長持ちする建物にする事が出来ます。
家の寿命を自ら縮めないよう、早めの対応を心がけましょう。
12.住居の雨漏りに目を向けましょう
今回は雨漏りについて長々とご紹介いたしました。
雨漏りが重篤化すると、建物がこのように変化してしまいます。
雨漏りを放っておく事がどれだけダメな事なのか、理解できると思います。
木造にとって、湿気や水は大敵です。
木造なのに雨漏りを起こしているなんていう状態は、建物を壊す為に行っているような事です。
常日ごろから、ご自身の身を守る住居に少しだけ目を向けて見たらよいと思います。